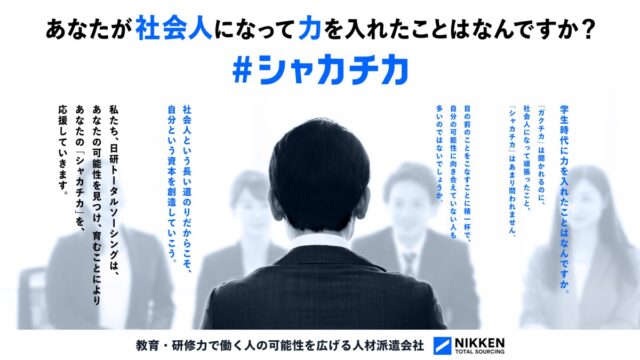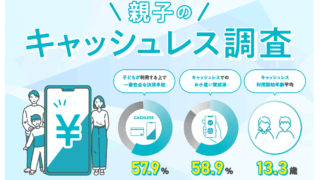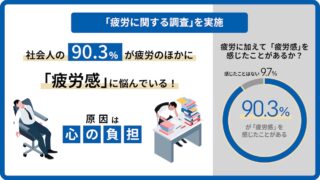東京・神田明神ホールで5月15日に開催されたProductZine Dayに、株式会社Wellnize 代表取締役 兼 執行役CEOの木下寛大氏が登壇。「腸プロダクトマネジメント 大企業×ベンチャーの『内なる外』で生まれる共生型新規事業開発」と題し、大企業とベンチャーの共生から生まれた腸内タイプ別パーソナルケアサービス「インナーガーデン」の開発秘話を語りました。

【木下氏プロフィール】
木下寛大
株式会社Wellnize 代表取締役 兼 執行役CEO
株式会社Co-Lift 代表取締役 共同CEO
楽天でデータサイエンティスト、データエンジニア、プロダクトマネージャーを経験後、起業。ビジネスコンサルティングやソフトウェア開発事業を展開する中で、2024年3月、食品大手の明治との合弁会社として株式会社Wellnizeを設立。
大企業とベンチャー、ちくわと腸:共通する「内なる外」の関係性
木下氏はまず、「ちくわの穴はちくわの中か外か?」「腸管は体の中か外か?」という問いかけから講演をスタート。どちらも構造的には「外側」でありながら、内側とも繋がる「内なる外」の存在であることを示し、この構造が今回の新規事業開発における大企業とベンチャーの関係性にも通じると説明しました。
株式会社Wellnizeは明治の関連会社でありながら、独立したガバナンスシステムを持つ「外側」の存在。明治の豊富な食品に関する知見やブランド力を活かしつつ、Wellnizeのデジタルサービス開発力やスタートアップならではのスピード感を融合させることで、大企業では難しい新規事業開発を可能にしたといいます。
「インナーガーデン」とは?

インナーガーデンは、自宅でできる腸内フローラ検査キットと、検査結果に基づいてパーソナライズされたココア味のドリンクを定期配送するサービスです。腸内細菌は約1000種類、数十兆個も存在し、その種類やバランスは人によって大きく異なります。同サービスでは主要な腸内細菌5種類のバランスを分析し、それぞれの菌が好むエサ(食物繊維など)を配合したドリンクを提供することで、効率的な腸活をサポートします。

プレボテラ
玄米やお魚、海藻など日本古来の食生活を行ってる人に増えている腸内タイプ(キシロオリゴ糖、フラクトオリゴ糖を含有)。

ルミノコッカス
最近女性に増えている腸内タイプ(イヌリン、フラクトオリゴ糖を含有)

バクテロイデス
最近日本人に増えている、欧米型の肉食の食生活を行ってる人に増えている腸内タイプ(シクロデキストリン、フラクトオリゴ糖を含有)。

フィーカリバクテリウム
運動をよくする、アスリートなどに多いと言われている腸内タイプ(ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖を含有)。

ビフィドバクテリウム
普段からヨーグルトをよく食べ、ビフィズス菌などを摂取している人に多い腸内タイプ(ラフィノース、フラクトオリゴ糖を含有)。
無理ゲーを乗り越えた挑戦
木下氏はインナーガーデンの開発において直面した困難と、それをどのように乗り越えたかをエピソードを通して紹介しました。
業務プロセスの壁:D2CとB2Bのギャップ
明治はB2B企業であるため、既存の業務プロセスは卸売を前提としており、D2Cビジネスであるインナーガーデンには適合しない部分が多くありました。例えば、会計上の要件により、ローンチが遅れる可能性もあったといいます。
この問題に対し、Wellnizeが販売会社機能を担うことで解決。明治はWellnizeに商品を卸し、Wellnizeが顧客に直接販売するスキームを構築することで、既存の業務プロセスを変更することなく、D2Cビジネスを実現しました。
商品タイプの不足:ユーザーへの分かりやすさと製造の難しさ
腸内フローラ検査では5つの腸内細菌タイプに分類されますが、製造上の制約から、当初は3種類のドリンクしか用意できませんでした。しかし、5種類の菌タイプに対して3種類のドリンクではユーザーにコンセプトが正しく伝わらないと考えた木下氏は、5種類のドリンク開発を強く訴え続けました。
これに対し明治の担当者は、素材の選定、商品開発、製造調整などを超特急で進め、ローンチに間に合わせて5種類のドリンクを完成させました。
成功の秘訣:メタ視点とパッション
木下氏はこれらの困難を乗り越えられた要因として、「メタ視点」と「パッション」の2つを挙げました。「メタ視点」とは、一見不合理に見える事象も、相手の立場や論理を理解した上で、なぜそうなっているのかを深く考えること。インナーガーデン開発では、大企業とベンチャーのカルチャーの違いを理解し、相手の論理を尊重しながら建設的な議論を重ねることが重要だったといいます。
「パッション」とは、成功するまで諦めずに挑戦し続ける強い意志。多くの困難に直面しても、必ず解決策があると信じ、情熱を持って取り組むことで無理ゲーを乗り越えることができたのです。
株式会社Wellnize 代表取締役 兼 執行役CEOの木下寛大氏から読者へのメッセージ
株式会社Wellnizeは、明治との合弁会社という大企業とベンチャー企業の「共生関係」によって生まれました。この関係性は、体内にありながら体外とつながる腸と腸内細菌の関係に例えられます。一見すると相容れない両者が、それぞれの強みを活かし、弱みを補完し合うことで、新たな価値を生み出す。その象徴的なサービスが、腸内タイプ別パーソナルケアサービス「インナーガーデン」です。
インナーガーデンは腸内細菌検査と、その結果に基づいたパーソナライズドリンクを提供するサービス。開発においては、大企業とベンチャーのカルチャーギャップ、既存の業務プロセスとの不適合、パッケージデザインの方向性の違い、商品種類の制約など、数々の困難に直面しました。しかし、われわれWellnizeと明治の担当者は、以下の2つのポイントを重視することで、これらの「無理ゲー」を乗り越えてきました。
メタ視点:問題を俯瞰的に捉え、相手の立場や論理を理解した上で、なぜそのような状況になっているのかを深く考える。
パッション:成功を信じ、最後まで諦めずに挑戦し続ける情熱。
これらの困難を乗り越えて生まれたインナーガーデンは、明治の持つ食と健康の知見・ブランド力と、Wellnizeのデジタル技術・スタートアップ精神が融合した、まさに「共生」の賜物といえるでしょう。
現在、売上も順調に伸びており、さまざまなメディアでも取り上げられています。今後はサービス拡大とともに、商品バリエーションの増加や海外展開も視野に入れ、さらなる成長を目指していきたいです。とにかく「自分に合った腸活ソリューションを見つけること」が重要です。インナーガーデンは、まさにそのための最適な選択肢となるでしょう。

ProductZine Dayの会場となった神田明神ホールのロビーに設置されたWellnizeブースには、多くの来場者が足を運んでいました。インナーガーデンの割引クーポンが当たるカプセルトイも大人気。
記者のような古い人間にとって、ベンチャー(中小企業)と大企業の関係は「互角ではない」「結局は大企業のいいなりにならざるを得ない」という考えが未だに強く根付いています。でも今回の木下氏のお話を聞いていると、大企業にないノウハウと情熱を持っていれば、ベンチャーでも対等に渡り合えるということがよくわかりました。そして、ここから生まれたインナーガーデンは、人間が抱える腸の悩みを解説する希望になるやもしれません。開発・販売までにさまざまなドラマが繰り広げられたこの腸活ドリンクを、ぜひ一度お試しあれ。
Inner Garden:https://floracheck.meiji.co.jp/