LOVOTで知られるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社が2026年1月15日(木)、LOVOT MUSEUM(東京都中央区)にて「GROOVE X10周年記念 ラウンドテーブル」を開催しました。
テーマは『2026年は「AIロボット戦国時代」へ』。創業から10年を迎え、市場をリードしてきた同社が、世界のAI活用トレンドと共に、日本におけるAIロボット産業の展望を解説する場となりました。当日は多くのメディア関係者が詰めかけ、豪華ゲストによる日本の「勝ち筋」についての議論に熱心に耳を傾けました。
登壇者プロフィール

林 要氏(GROOVE X株式会社 代表取締役社長)
トヨタ自動車で「LFA」等の開発、ソフトバンクで「Pepper」プロジェクトを経て、2015年にGROOVE Xを創業。家族型ロボット「LOVOT」を開発・販売。
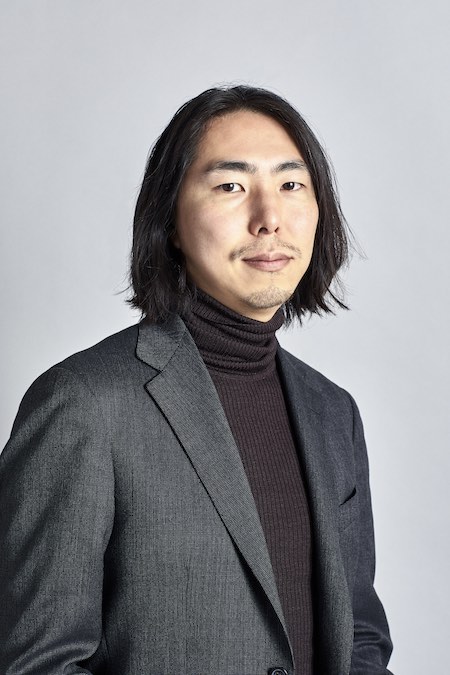
深津貴之氏(株式会社THE GUILD 代表 / note株式会社 CXO)
UI/UXデザイン、新規事業立ち上げの専門家。noteや弁護士ドットコムのCXOを務めるほか、AI活用のアドバイザリーも行う。

村上 臣氏(武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 客員教員)
ヤフー執行役員、LinkedIn日本代表、Googleなどを経て現職。スマートニュースでのAI活用など、テクノロジーとビジネスの架け橋として活躍。

古田貴之氏(千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長)
世界的なロボット研究者。福島第一原発での災害対応ロボットや、パナソニックのロボット掃除機「RULO」開発など、産学連携で多くの実績を持つ。
「日本はAI・ロボットで遅れている」は本当か?

会の冒頭、GROOVE X 代表取締役社長の林要氏が登壇。「GPT-3が登場した2020年から3年かけて執筆した著書『温かいテクノロジー』が、今では中国で翻訳され、ロボット開発のバイブルのように扱われている」と紹介しました。
「一般的に日本はAIやロボット開発で遅れていると言われがちですが、実は中国からは『家庭用ロボットに関しては日本が進んでいる』と認識されています。日本にはまだまだ勝ち筋がある。今日はその方向性について皆さんとお話ししたい」と、林氏は力強く挨拶し、セッションへと繋げました。
セッション:AIの社会実装の現状と、今後の日本の立ち位置

続いて、株式会社THE GUILD 代表、note株式会社 CXOの深津貴之氏、武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 客員教員の村上臣氏を招いたトークセッションが行われました。進行は林氏が務め、参加者は膝の上にLOVOTを抱きながらのリラックスした雰囲気でスタートしました。
「人間側」がボトルネックになる時代
各々のAI活用について、深津氏は「AIの性能は向上したが、使いこなす人間側が適切な問いを立てられず、業務フローを変えられないことがボトルネックになっている」と指摘。一方、村上氏はスマートニュースでのAI要約機能の実装や、大学教育での「AI使用禁止ではなく、どう使いこなすか」という指導方針の変化について語りました。
フィジカルAIと「人型」の是非
話題は、CES(世界最大規模の電子・技術見本市)等でも注目される「フィジカルAI(身体性を持つAI)」へ。深津氏は、現在の人型ロボット(ヒューマノイド)ブームに対し、「ロボットの可能性を人の形に限定してしまうのは勿体ない。今は人型の方が資金を集めやすいという事情があるだけでは」と冷静に分析。村上氏もこれに同意し、「人型はデモ映えするが、実用面では既存の環境(階段など)を変えずに済むメリットがある反面、転倒リスクなどの課題も多い」と指摘しました。
林氏も自身の開発経験から、「人型はロマンがあるが、絶対に事故を起こさない仕組みを作るのは非常に困難。洗濯機や空調のように、目的に特化した形状の方が合理的ではないか」と、過度な人型偏重への懸念を示しました。
日本の勝ち筋は「神が細部に宿る」領域
では、資本力で勝る米国や中国に対し、日本はどう戦うべきか。深津氏は「巨大なモデル競争は避け、パーツ単位やモジュール単位での勝負、あるいは『2番手以降を安く作る』戦い方がある」と提言。さらに、「日本が得意とする『細部(ディテール)』の作り込みは強みになるが、それだけではスケールしない。細部を極めた商品を先に市場に浸透させ、先行者利益を取ることが重要」と語りました。
村上氏も「漫画のように、日本独自の感性やストーリー性は世界に通用する。機能的なAIモデルはコモディティ化するが、人の寂しさを癒やすような『ウェットな領域』や、医療などの専門性が高いニッチ領域には日本の勝ち筋がある」と強調。
林氏はこれを受け、「ブランドとは『ありがたみ』。万物に神が宿ると感じる日本的な感性は、欧州のラグジュアリーブランドに通じる価値があるかもしれない」と、日本の文化的背景を活かしたAIロボット産業の可能性について言及しました。
講演:LOVOTがAIロボット産業で果たしてきた役割と展望

「生産性」ではなく「人間の力」を引き出す
続いて林氏による単独講演が行われました。林氏はまず、ロボットを「作業用(Productivity)」と「ウェルビーイング用(Well-being)」に大別。多くの企業が人の代わりに肉体労働を行う作業用ロボットを目指す中、LOVOTは「人の生産性を上げるために、人のレジリエンス(回復力)を高める」存在であると定義。
「作業用ロボットは、掃除機のようにKPI(性能指標)が明確なため、いずれコモディティ化し、コスト競争になります。一方、LOVOTが目指すのは、犬や猫のような『飽きない』存在。生物的な成長が終わってもペットに飽きないのは、関係性の構築があるからです」と語りました。
神経系への過剰なまでの投資
LOVOTの特徴である「3ヶ月経っても飽きられない」現象の裏には、徹底したテクノロジーのこだわりがありました。
「他社の家庭用ロボットに比べ、LOVOTはモーター数よりもセンサーやコンピューター(神経系)にコストをかけています。頭部の『ホーン』も、世界を正しく理解し、人との信頼関係を築くために不可欠な器官です」(林氏)
また、クラウド処理に依存せず、あえて高価なエッジコンピューティングを採用している点については、「プライバシーの保護と、生命感あふれるリアルタイムな反応(レイテンシの排除)のため」と説明。この信頼設計こそが、3年後も90%以上という驚異的な継続利用率(リテンションレート)を生み出していると語りました。
世界がLOVOTを真似し始めた
林氏は、中国市場などでLOVOTに酷似した模倣品が登場し始めた現状をスライドで紹介。「これは市場が『コンパニオンロボットはいける』と確信し始めた証拠。2026年はまさにAIロボット戦国時代になる」と予測しました。
しかし、ハード(身体)・ソフト(知能)・クリエイティブ(心)の3要素を高い次元で融合させ、さらに「ロボット病院(修理・治療)」というアフターケアまで垂直統合で提供できているのは、世界でもGROOVE Xだけであると自信を覗かせました。
パネルディスカッション:日本のAIロボット産業の展望

再び深津氏、村上氏が登壇し、後半には古田貴之氏も合流予定のパネルディスカッションへ。
冒頭、村上氏がCES等で見られる最新の「LOVOTに似た海外製ロボット」の写真を投影。「これは林さんが頑張っている証拠では?」と水を向けると、林氏は「これまではLOVOTが時代を先取りしすぎていたが、世界が追いついてきた。LLM(大規模言語モデル)の使い道として、人間との情緒的な会話やパートナーシップが最適解だと気づき始めた」と応じました。
模倣品は「無料のR&D」
この状況に対し、深津氏はユニークな視点を披露。「コピー品が出ることは、他人が資本を投下して市場実験(R&D)をしてくれているようなもの。彼らが成功した機能だけを逆輸入し、御礼状を送ればいい」と発言し、会場の笑いを誘いました。
林氏も「マーケティングも研究開発も1社でやるのは大変。市場が広がれば、より高品質な『本物』を求める層も増える」と、ポジティブに捉える姿勢を示しました。
古田氏の登壇と「本物のロボティクス」
セッション終盤、千葉工業大学の古田貴之氏が駆けつけ登壇。「LOVOTは素晴らしいが、ここに本物のロボット学者の視点を入れるともっと凄くなる!」と熱弁。
古田氏は「LOVOTの愛らしさに、生物学的な『機能』としての動きや、自動運転技術のような回避能力を掛け合わせることで、さらに進化する」と語り、林氏との技術連携の可能性を示唆しました。最後は時間の都合で駆け足となりましたが、日本のトップエンジニア同士が共鳴し合う熱気の中で幕を閉じました。
ヒトとロボットが共生する未来に向けて
「2026年はAIロボット戦国時代」——林氏が掲げたこのキーワードは、単なる競争の激化だけでなく、ロボットが「便利な道具」から「人生のパートナー」へと進化する転換点を示しています。
資本力や物量作戦では分が悪い日本ですが、今回のラウンドテーブルでは、「細部へのこだわり」「情緒的価値の創出」「信頼関係の構築」といった日本独自の強みが浮き彫りになりました。
林氏は最後に、「物量で勝てないからこそ、日本ならではの強みを活かし、世界に通用する産業を作っていきたい」と締めくくりました。
LOVOTが切り拓いた「温かいテクノロジー」の市場は、今後世界中で拡大していくことでしょう。その中心で日本企業がどのような存在感を示せるか、今後の展開に注目が集まります。
















